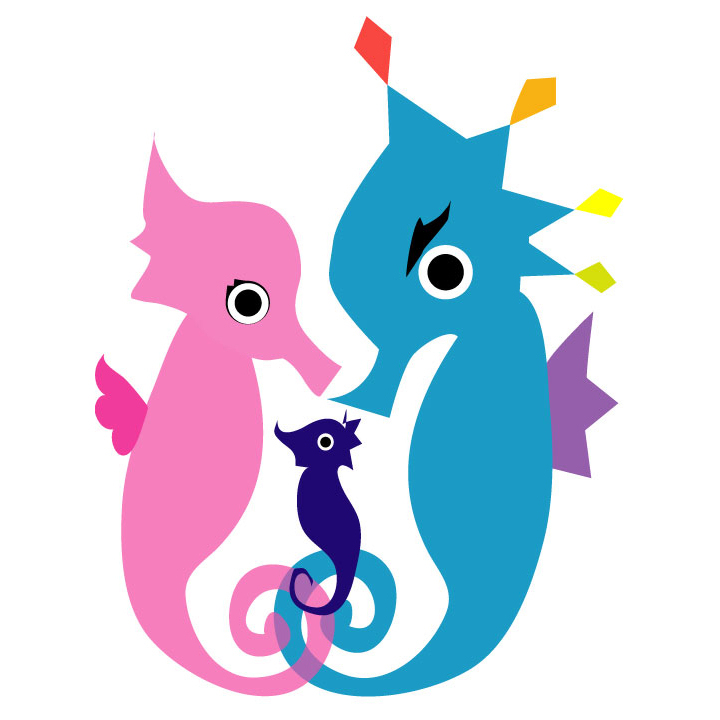■基本概念
サウンドスケープ(Soundscape)「音風景」という言葉があります。サウンドスケープとは「ある場所・環境の音の風景や音環境を総体として捉え、その価値や意味を探る考え方」です。カナダの作曲家・音響研究者 R. マリー・シェーファー(R. Murray Schafer) が1970年代に提唱した概念で、単なる環境音の録音ではなく、音と人・文化・自然との関係性に注目します。ここに持続可能な素材循環を適用するのがシーホース工房の提唱する《手作り楽器サウンドスケープ》です。自然の恵みで得られた手作り楽器の音をその土地のサウンドスケープに還元することで、新たな音風景を創り出します。《忘れられた街の音風景を描く》というコンセプトを掲げ、それぞれの町に固有の風土や文化に根差した手作り楽器サウンドスケープを展開します。そこから町の魅力を再発見し、後世に残すべきものを保存し、それを発信することで市民を元気にするというモチベーションを活動のエンジンとして参ります。
■実践のプロセス
1. 基盤フェーズ(0〜6ヶ月)
月例ワークショップの位置づけ
- テーマ設定
毎月「音のテーマ」を決める(例:「風の音」「水の音」「街のリズム」「夜の森」)。 - 内容構成
- 手作り楽器制作(竹笛、スリットドラム、絃楽器など)
- 簡単なアンサンブル練習
- 音環境(周辺の環境音)を録音し、楽器演奏に組み合わせる実験
- 記録
- 演奏と映像をアーカイブ(短編動画・サウンドマップ)
- SNSで公開し、徐々に外部への興味を誘う
2. 拡張フェーズ(6〜12ヶ月)
小規模公開イベント
- 形式:
ワークショップ参加者と一般観客が一体になれる構成- 前半:参加者の演奏と環境音コラージュ
- 後半:主催者映像演出+アンサンブル(プログラミングによるリアルタイム映像合成)
- 場所:
公民館ホール、カフェ、ギャラリー - 市民参加の形態
- 観客もその場で簡単な楽器を作って最後の曲に参加
- 会場周辺で短時間の「サウンドウォーク」→その音をライブで使用
3. 広域フェーズ(1〜2年)
屋外イベント/街づくり連動
- サウンドスケープ・フェス
- 午前:市民楽器づくりブース(竹笛・パーカッション)
- 午後:サウンドウォーク(街の音を採集)
- 夕方:大アンサンブル&映像投影(壁面や広場にプロジェクションマッピング)
- 地域連動ポイント
- 商店街の人に「音の暖簾」的な参加を依頼(店先に楽器を置き自由に鳴らせる)
- 地元史跡や名所の音を採取し、「音の観光ガイド」として配信
- 持続性
- 年1回の恒例イベントとして定着
- 学校・福祉施設との連携(地域教育・生涯学習)